多くの日本人は、学校や職場で「税金」についてきちんと教わる機会がないまま社会に出ています。
とくに会社員は、会社が税金を自動で計算・徴収してくれるため、「自分の税金がどう決まっているのか」を知らない方も多いのが現実です。ですが、税金のしくみを正しく知っておくことで、「ムダに払わずに済む」ケースも意外とあるんです。
この記事では、サラリーマン・パート・アルバイトの方に向けて、「所得税」と「住民税」の違いや計算方法、知っておくと得する節税の基本をわかりやすく解説します。
所得税と住民税の基本
所得税とは?
所得税は、国に納める税金で「1年間の所得(収入-控除)に応じて課税される仕組み」です。
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。(出典:国税庁)
所得控除とは「この分は課税の対象にしなくていいですよ」という差し引き制度のこと。つまり、実際の収入すべてが税金の対象になるわけではありません。
たとえば年収400万円の人が、各種控除によって200万円しか課税対象にならない場合、税金はその200万円に対して計算されます。この金額を「課税所得」と呼びます。
住民税とは?
住民税は、あなたの住んでいる「都道府県・市区町村」に納める地方税です。
住民税(じゅうみんぜい)は、都道府県民税と市町村民税を合わせていう語。(出典:Wikipedia)
地域の行政サービスに使われるお金で、都道府県と市町村が共同で徴収します。
所得税の計算方法【簡単な例で解説】
ケース①:パートで年収100万円
所得控除には、以下のような「誰でも使える控除」があります。
- 基礎控除:48万円
- 給与所得控除:最低55万円(収入により変動)
年収100万円の方であれば、控除額は合計103万円となり、収入<控除となるため課税所得はゼロ。つまり「所得税は非課税」です。
✅ これがいわゆる「103万円の壁」です。
ケース②:会社員・年収400万円・生命保険に加入
【想定条件】
- 社会保険料:60万円(健康保険・年金)
- 生命保険料:6万円
- 医療保険料:2万円
【控除一覧】
- 基礎控除:48万円
- 給与所得控除:124万円(年収400万円)
- 社会保険料控除:60万円
- 生命保険料控除:6万円(上限適用)
合計控除:238万円
課税所得:400万円 − 238万円 = 162万円
税率:5%(課税所得195万円以下)
所得税:81,000円
所得税率表

2025年の税制改正で、基礎控除や給与所得控除の金額が一部変更されました。
(例:低所得者は基礎控除が最大で95万円に増加)
▶ 令和7年度 税制改正まとめ|控除の変更点をわかりやすく解説
年末調整と源泉徴収の仕組み
会社員やアルバイトの場合、給与から毎月ざっくり計算された所得税が天引きされます(源泉徴収)。しかし、実際の所得控除などを反映した正しい税額は年末に「年末調整」で計算し直され、払いすぎていた分は還付されます。
このとき、生命保険料控除などを申告し忘れると、損する可能性があるので注意です。
所得控除の一覧と活用方法
所得税では、以下の15種類の控除が用意されています。
| 区分 | 内容例 |
|---|---|
| 基礎控除 | 全員が対象(48万円) |
| 給与所得控除 | 給与を受けている人のみ |
| 社会保険料控除 | 健康保険・年金など |
| 扶養控除 | 扶養家族がいる人 |
| 配偶者控除・特別控除 | 配偶者が一定収入以下の場合 |
| 医療費控除 | 年間10万円超の医療費など |
| 寄附金控除 | ふるさと納税など |
| 生命・地震保険控除 | 加入している保険による |
| 学生・障害者控除 | 条件を満たす場合に適用可能 |
控除を適用できるものが多いほど、課税所得が減り、節税効果が高まります。
税額控除との違い|直接減税できる仕組み
「所得控除」は課税所得を減らすのに対し、「税額控除」は最終的な税金から直接差し引く制度です。
代表的な税額控除:
- 住宅ローン控除(10年間で数十万円の減税も)
- 外国税額控除(海外株式に投資している場合)
- 寄附金特別控除(認定NPOなどへの寄付)
税額控除は節税効果が大きいため、対象となる方は必ずチェックしましょう。
住民税の計算方法と注意点
住民税は以下の2つで構成されています。
| 種類 | 説明 | 金額例 |
|---|---|---|
| 所得割 | 課税所得の10% | 所得によって変動 |
| 均等割 | 所得に関係なく一律 | 年5,000円(標準) |
※均等割は地域によって上乗せがある場合もあります。
住民税にも所得控除が適用されますが、基礎控除が43万円と所得税より5万円少ない点に注意が必要です。そのため、「年収102万円」などの場合、所得税はかからなくても住民税は発生します。
節税の第一歩は「知ること」から
節税といえば、以下のような制度をよく耳にするかもしれません。
- ふるさと納税:寄附金控除で実質2,000円の負担で返礼品がもらえる
- iDeCo(イデコ):老後の資産形成と所得控除が同時にできる
ただし、こうした制度も「きちんと理解して活用する」ことが重要です。特にiDeCoは途中解約ができないため、無理のない範囲で始めましょう。
iDeCoについて詳しく知りたい方はこちら
▶ iDeCoのメリット・デメリットをわかりやすく解説
まとめ|税金のしくみを知れば、節税もできる
所得税・住民税は「課税所得 × 税率」で決まります。そして、課税所得を減らすためには、各種控除の活用が重要です。
知らないうちに損をしていることがないよう、年末調整や確定申告のタイミングで自分の税金に目を向けてみましょう。
節税は、まず“知ること”から始まります。
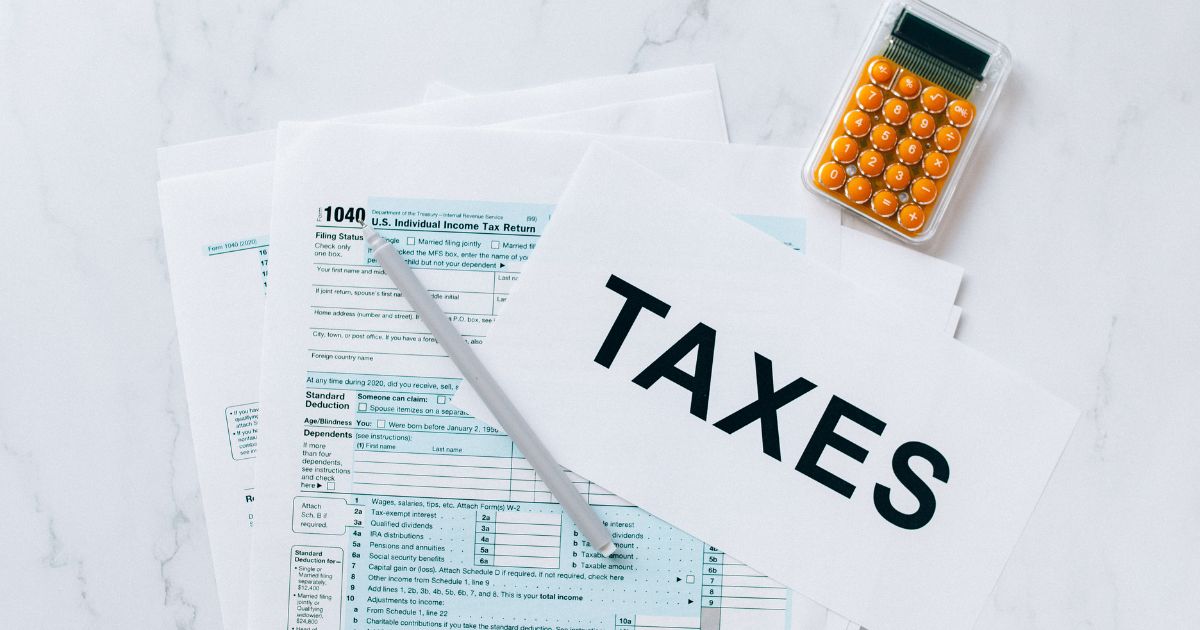


コメント